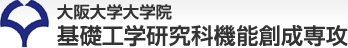- ホーム
- 機能創成セミナー
機能創成セミナー Seminar on Mechanical Science and Bioengineering
|
第218回
|
2026年2月2日(月) 14:30-16:00 [February 2nd 2026 (Mon) 14:30-16:00] 基礎工学研究科 C419(C棟共用セミナー室) |
|---|---|
| Now You Will See the Engineer: Diseases That Medicine Cannot Cure but Engineers Might | |
|
Mathematical modelling and computer simulation have proved tremendously successful in engineering. One of the greatest challenges for mechanists is to extend the success of computational mechanics to fields outside traditional engineering, in particular to biology, biomedical sciences and medicine.
Over many decades of work in biomechanics for medicine I have come to realise that little progress in effectiveness of management of some diseases may be due to the fact that their understanding needed to choose an optimal treatment option requires mastery of concepts from mechanical, civil, electrical and mechatronic engineering, rather than chemistry, biology and physiology medical professionals are trained in and familiar with. Three examples I will consider today are:
i) Risk assessment and stratification of patients suffering from abdominal aortic aneurysm (AAA) disease [1].
ii) Assessment of physiological significance of coronary artery stenosis [2].
iii) Epileptic seizure onset zone (SOZ) localisation [3]
In my lecture I will attempt to illustrate how fundamental engineering concepts can help in the above cases, potentially leading to better health outcomes and dramatic reduction in costs.
I will conclude with suggestions for the future developments in the field and a vision for a new era of personalised medicine based on patient-specific scientific computations. Keywords: computational science, biomechanics, brain, vascular system References [1] Mostafa Jamshidian, Adam Wittek, Saeideh Sekhavat, Hozan Mufty, Geert Maleux, Inge Fourneau, Elke R. Gizewski, Eva Gassner, Alexander Loizides, Maximilian Lutz, Florian K. Enzmann, Donatien Le Liepvre, Florian Bernard, Ludovic Minvielle, Antoine Fondanèche, Karol Miller (2025). Towards personalised assessment of abdominal aortic aneurysm structural integrity. arXiv preprint arXiv:2502.09905. [2] BF Zwick, K Mirota, J Chojnacki, M Gajowczyk, K Miller (2025) “Reliable computational fluid dynamics for ground truth generation for AI-based blood flow analysis”. In: Kobielarz, M., Wittek, A., Nash, M.P., Nielsen, P., Babu, A.R., Miller, K. (eds) Computational Biomechanics for Medicine. MICCAI 2024. Lecture Notes in Bioengineering. Springer, Cham. doi.org/10.1007/978-3-031-94128-3_3 [3] Benjamin F. Zwick, George C. Bourantas, Saima Safdar, Grand R. Joldes, Damon E. Hyde, Simon K. Warfield, Adam Wittek, Karol Miller (2022) “Patient-specific solution of the electrocorticography forward problem in deforming brain”, Neuroimage. 263/119649. |
|
| Karol Miller (Intelligent Systems for Medicine Laboratory, The University of Western Australia, Perth.) | |
| 世話人:大谷智仁 | |
|
第217回
|
2025年12月19日(金) 12:10-13:10 [December 19th 2025 (Fri) 12:10-13:10] 基礎工学研究科 C棟4階共用セミナー室 |
| Development of resolved and unresolved CFD–DEM coupling simulation of three-phase flows | |
| Gas-liquid-solid three-phase flows are encountered in many industrial processes such as wet granulation and slurry mixing. Despite a long history of research, our knowledge today about such flows is still limited due to the complex interactions between multiple phases, e.g., surface tension, drag force and particle surface wetting. Therefore, there is an increasing demand for the development of reliable simulation models for better understanding and optimisation of the processes. In this talk, the recent advancements in CFD–DEM coupling models for three-phase flows are discussed. Both resolved and unresolved models have been developed to simulate flows from small (particle) scale to large (industrial) scale. | |
| 鷲野公彰(大阪大学大学院工学研究科・准教授) | |
| 世話人:後藤晋 | |
|
第216回
|
2025年9月29日(月) 11:00-12:00 [September 29th 2025 (Mon) 11:00-12:00] 基礎工学研究科 D棟4階共用セミナー室 |
| Two Surprising Links Between Convection Velocities and Non-Linearities in Wall-Bounded Turbulence | |
| Coherent large-scale motions in turbulence are major contributors to important environmental and engineering flow phenomena, from river sediment dynamics and wind farm power fluctuations, to heat and momentum transport near walls or along ocean waves. Determining the convection velocities of these large-scale motions is crucial for inferring their spatial structure from temporal field measurements; for developing mode-based models for turbulence prediction; and for developing new actuation schemes for controlling turbulent flows. In this talk, I will explore two surprisingly divergent aspects of the convection velocities of large-scale structures in turbulence. I will first show how accounting for non-linear interactions broadens the predicted spectrum of convection velocities in turbulence modeling, and then, contrariwise, how convection velocity variations can easily be mistaken for evidence of non-linear interactions. The first problem will be examined through laboratory experiments and modeling and has implications for developing more accurate predictions of the space-time spectrum of turbulence. The second problem is an analytical re-examination of the widely used amplitude modulation coefficient but has broader implications for identifying non-linear dynamics in any experimental system. | |
| Ian Jacobi (Technion Israel Institute of Technology) | |
| 世話人:後藤晋 | |
|
第215回
|
2025年8月7日(木) 13:00-14:00 [August 7th 2025 (Thu) 13:00-14:00] 基礎工学研究科 C棟4階共用セミナー室 |
| Hydrogen Segregation and Embrittlement in Metals and Alloys | |
| Hydrogen is known to degrade the mechanical properties of many metals and alloys. The underlying mechanisms are incompletely understood. Challenges include the dynamic processes, and wide range of length and time scales that are involved. Here, I describe our development of in-situ techniques for studying hydrogen embrittlement using synchrotron transmission X-ray microscopy (TXM) and Kelvin Probe Force Microscopy (KPFM). Hydrogen segregation and embrittlement are compared in iron, nickel, and a nickel-based superalloy. Using KPFM, we find that mechanical strain leads to hydrogen segregation to high angle grain boundaries, which become the sites where fracture occurs. TXM is used to detect the formation of voids of ~100 nm to microns in size near the crack tip. In iron, we find that voids are elongated perpendicular to the loading direction, and highly localized at the crack tip during hydrogen charging in intergranular failure. Dynamic TXM imaging enables the observation of void-mediated crack growth, as well as the coalescence of the primary crack with secondary cracks. In-situ testing of Hastelloy reveals hydrogen segregation to phase boundaries at nano-precipitates, and the influence on crack propagation and void growth. | |
| Wendy Gu (Stanford University) | |
| 世話人:尾方成信 | |
|
第214回
|
2025年7月7日(月) 15:50-16:20 [July 7th 2025 (Mon) 15:50-16:20] 基礎工学研究科 B棟302教室 |
| 実験と数値計算による沸騰熱伝達の基本構造の理解 | |
| 沸騰熱伝達は他の伝熱形態と比較して高い熱伝達率を有している.この沸騰熱伝達を気体や液体の強制対流のみでは適切な動作温度以下に冷却することが難しくなっているCPUやGPU,パワー半導体などの高発熱密度体の冷却に利用する動きが高まっている.一方,沸騰がなぜ高い熱伝達率をもつかという問いに対する答えは現在も明確でなく,沸騰熱伝達メカニズムには不明な点が残されている.我々は,実験・数値計算による沸騰素過程の直接観察に基づいて現象理解を進める方針で研究を行ってきた.本講演では,高速度赤外線カメラを用いた壁面温度・熱輸送分布の可視化を通じて明らかにした,沸騰熱伝達を構成する各種伝熱素過程の局所伝熱特性や全熱輸送に対する寄与,限界熱流束発生機構などについて紹介する.また,実験を通じて水の沸騰において壁面熱輸送を支配していることが分かった対流熱伝達の伝熱機構を,数値計算で調べた結果についても紹介する. | |
| 矢吹智英(九州工業大学大学院工学研究院・教授) | |
| 世話人:後藤晋 | |
|
第213回
|
2025年7月7日(月) 15:10-15:40 [July 7th 2025 (Mon) 15:10-15:40] 基礎工学研究科 B棟302教室 |
| 界面相分離を伴う流動現象の実験・数値シミュレーションによる理解 | |
| 微小な空間で高粘性流体を低粘性流体が置換する際、Saffman-Taylor不安定性もしくはviscous fingering(VF)と呼ばれる指状の模様を呈する。そしてその2流体はこれまで非混和系、完全混和系で議論されてきた。近年、2流体が任意の割合で互いに混ざり合う部分混和系での研究がはじめられた。部分混和系VFでは完全混和系・非混和系とは定性的に異なり、指状ではなく多数の液滴を生成することが実験的に示された。そして化学ポテンシャル勾配に起因する自発対流によるKorteweg効果により、その液滴は自走することも確認された。数値シミュレーションもいくつか提案され、実験を再現できるものの報告もある。本講演では、実験とシミュレーションによる部分混和系VFダイナミクスとそのメカニズムについてまとめて紹介する。 | |
| 鈴木龍汰 (東京農工大学西東京三大学共同サステナビリティ国際社会実装研究センター・特任助教) | |
| 世話人:後藤晋 | |
|
第212回
|
2025年6月24日(火) 15:30-16:30 [June 24th 2025 (Tue) 15:30-16:30] 基礎工学研究科 D棟共用セミナー室 |
| Surprising thermodynamics of landfalling hurricanes | |
|
A hurricane over the ocean functions as a heat engine, its heat source being the moisture from the warm ocean. When a hurricane hits land, the heat source is lost, and consequently, it decays. This decay is considered to be a non-thermodynamic process. Contrary to this prevailing paradigm, we argue that thermodynamics plays a key role in the evolution of landfalling hurricanes and that the thermodynamic effect is orchestrated by the moisture stored in the hurricane from its journey over the ocean prior to landfall. This talk is based on joint research with Lin Li. 1. L. Li and P. Chakraborty, Slower decay of landfalling hurricanes in a warming world, Nature, vol. 587, pp. 230-234, 2020. 2. L. Li and P. Chakraborty, Birth of a cold core in tropical cyclones past landfall, Physical Review Fluids, vol. 6, article L051801, 2021. |
|
| Pinaki Chakraborty (Okinawa Institute of Science and Technology) | |
| 世話人:後藤晋 | |
|
第211回
|
2025年5月22日(木) 15:30-16:30 [May 22nd 2025 (Thu) 15:30-16:30] 基礎工学研究科 J棟 共用セミナー室 (J114室) |
| 列車・トンネル系の空気力学~新しい新幹線先頭部の開発~ | |
| 列車・トンネル系の空気力学では,圧縮性を考慮した理論解析,数値解析(CFD)およびマッハ数に基づく相似測を満たす模型実験などによって,列車のトンネル突入・退出,すれ違いなどによって生じる圧力波と列車周りの圧力場を研究している.例えば,列車のトンネル突入時に生じる圧縮波は,トンネル出口で生じる微気圧波を低減するため,圧縮波の勾配をなだらかにする先頭部形状を開発する必要がある.従来は,先頭部中央部では断面積変化率を一定にする形状が良いとされてきたが,最新の研究では,中央でも積極的に断面積変化を与える3段型先頭部が効果的であることを明らかとなった.これは,線形音響学,圧縮性を考慮したCFD,時速360 km/hで列車模型を発射する模型実験を駆使した成果である.本講演では,列車トンネル系の諸問題に対する鉄道総研での取り組みと,列車先頭部に関する最新の研究成果を紹介する. | |
| 宮地徳蔵 (公益財団法人鉄道総合技術研究所 熱・空気流動研究室 研究室長) | |
| 世話人:杉山和靖 |